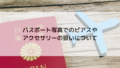お盆は日本の重要な行事で、地域によっては7月から行われることもありますが、
一般的には8月に行うことが多いです。
この時期には故人や先祖の霊を迎え入れる習慣がありますが、
具体的な墓参りの時期についてはしっかりと認識していますか?
適切な服装や礼儀を知ることは、この行事を敬う上で非常に役立ちます。
本文では、墓参りの適切な時期、服装、そして礼儀について詳しく説明します。
お盆の墓参りの主な時期
地域に応じてお盆の期間を確認することから始めます。
日本では、ほとんどの地域で8月15日を中心にお盆が行われますが、
地域によっては旧暦を使用する場所や7月にお盆を迎える地域もあります。
具体的な日程
- 8月13日から16日: 主に西日本や北関東以北で行われる月遅れのお盆。
- 7月13日から16日: 東京や南関東、函館、静岡旧市街地などで行われる7月のお盆。
- 旧暦7月15日: 沖縄や奄美大島などで行われる旧暦のお盆。
現在、新暦が使われているため、旧暦を使用する地域では毎年お盆の日付が変動します。
墓参りはどのタイミングで行うか
お盆の初日には、迎え火を行い、先祖の霊を自宅に迎え入れるためにお墓で行います。
この行事は、先祖の霊が無事に自宅まで戻ってこれるようにするため、
かつて目連尊者が施餓鬼という供養を行った伝統に基づいています。
この伝統は、故人が餓鬼道にいる母親を救うために始まりました。
現在も日本のお盆では、先祖の霊に食事を供えて供養を行います。
最初に先祖の霊を迎えることからお盆は始まり、
そのためお墓参りはお盆の入りに行うのが一般的です。
地域によっては迎え火を自宅の門口で行うところもあり、
これは自宅がどこであるかを故人に知らせる目印としています。
お盆の際の墓参りに適した服装
お盆の際には、理想的には喪服を着用するのが望ましいとされますが、
実際にはお盆の服装に厳格な規定はありません。
故人との関係が遠い場合や、知人のお盆に招かれた際は、
フォーマルな服装が適切かもしれませんが、家族や親しい親戚と共に過ごす場合は、
カジュアルな服装でも問題ありません。
法事やその他の正式な儀式では黒を基調とした服装が必要ですが、
お盆自体に特定の服装規定はないため、親しい間柄なら普段着でも構いません。
ただし、他の親戚と服装を合わせることがあれば、周囲に合わせることが重要です。
また、遺族を訪れる際は、過度に派手な服装や露出の多い服、強い香水は避けるべきです。
新盆の場合は法要が行われることもあるため、喪服を用意しておくと良いでしょう。
墓参りの作法とマナー
墓参りに関する特別な作法は存在しませんが、基本的な手順はありますので紹介します。
最初に寺院の本堂に参拝する
寺の墓地を訪れる場合は、最初に本堂への参拝から始めます。墓地に入る前に本堂で一礼をするのが良いでしょう。また、無縁墓があれば合わせて参拝することも推奨されます。
手を清めてから墓地に向かう
入口で手を洗い清め、手桶に水を汲んでからお墓に進みます。手桶やひしゃくは多くの場合、墓地で借りることができます。
お墓に到着したらまずは一礼
お墓の前で手を合わせ、祖先への挨拶をします。隣のお墓に対しても礼をすることが望ましいです。
墓周りの掃除を行う
お墓の周囲の草を抜き、墓石を清掃します。
落ち葉や枯れ花は取り除き、全体をきれいにすると良いでしょう。
墓石は固く絞ったタオルやスポンジで洗い、細かい部分は歯ブラシを使うことが推奨されます。
墓石に冷水をかけるのは避けるべきです。
お供え物を置く
お供えする花は、次に来た時に倒れていないように茎を短く切ります。
お菓子などの供物は、器や半紙にのせて供えます。
お線香は、最初に束で火をつけ、煙が出たら手で扇いで消します。
これにより、供養されていない霊が近づきにくくなります。
お線香の供え方
お線香を供える方法は、立てて供える場合もあれば、横に寝かせて供える場合もあり、
これは宗派によって異なります。
最初に束でお線香を焚いた後、参列者が一人ずつお線香を取り、順番に供えていきます。
この際、故人と特に近い関係だった人や、直系の親族から供えるのが一般的です。
礼拝と合掌
心を込めて手を合わせ、合掌しながら故人や祖霊の幸せを祈ります。
故人への感謝を心に留めてお祈りすると良いでしょう。
また、墓前での法要の際は、座ることが難しい方のために、
持ち運び可能な折りたたみ椅子を用意すると配慮になります。
祈りの手順
お墓の正面に向かって、静かに手を合わせます。
数珠は宗派によって持ち方が異なりますが、一般的には胸の前で左右の手を合わせて持ち、目を閉じます。
祈りの際は、頭を軽く傾けて、心の中で伝えたい言葉や報告したいことを唱えます。
清掃と片付け
お供え物は放置すると野生動物に荒らされる可能性があるため、帰る際には持ち帰ります。
また、使用したひしゃくや手桶は元の場所に戻し、お墓周りは清潔に保つことが大切です。
お墓の風化を防ぐためにも、墓地に水をまくことは推奨されません。
お供え物の後の取り扱いについて
供えた後の食べ物は家庭で安心して食べることができます。
日本には、神様や先祖に供えた食物には清浄なエネルギーが宿るとする同食信仰という習慣があります。
供え物をいただく際には、感謝の意を込め、祖霊との共有という心持ちで美味しく召し上がることが推奨されます。
お墓参りの持ち物について
お墓参りに必要な物品を紹介します。
一部の墓地ではバケツや箒を貸し出している場合がありますので、持参する必要がありません。
お墓参りで持参するもの/掃除道具
- ほうき
- 軍手
- ゴミ袋(枯れた花や落ち葉を収集するため)
- 雑巾
- たわし・スポンジ・歯ブラシ
- 墓石専用洗剤(頑固な汚れに)
- ザル(玉砂利を洗う際に使用)
- バケツ
お墓参りで持参するもの/供養・お参り
- ロウソク
- マッチまたはライター
- お線香
- お供え物(お菓子など)
- お花
お墓の掃除方法
墓石清掃において
墓石を清掃する際は、専用の石材洗剤を使用します。
使用前には目立たない部分で試し、スポンジや柔らかい布で拭くことをお勧めします。
硬いブラシは墓石を傷つける可能性があるため避けましょう。
彫刻部分の洗浄
彫刻された部分の汚れは、スポンジや雑巾だけでは取り除きにくい場合があります。
このような場合、歯ブラシを使用して優しく洗浄すると効果的です。
ステンレス製品の洗浄
ステンレス製の線香皿や花筒などは、取り外して水洗いし、最後に乾いた布で水分を拭き取ります。
これにより、墓地の湿気で発生する苔やカビの問題を防ぐことができます。
お盆のお墓参りができない場合
お盆にお墓参りができない場合がありますが、それによって故人や祖霊に失礼があるわけではありません。
一番大切なのはその気持ちであり、可能であればお盆前に墓参りをして事情を伝えると良いでしょう。
心の中で「今年はご一緒できず申し訳ない」と伝えれば、その思いはきちんと届きます。
お参りは事前に行うことで、故人や祖霊に感謝の気持ちを伝えることが可能ですが、
早めに行けない場合はお正月や帰省の際に墓参りをして心を伝えましょう。
また、気持ちを表したい場合には日持ちするお菓子を供えて郵送する方法もあります。
お盆の意味
お盆は、先祖や故人の霊が一時的にこの世に戻る期間とされています。
多くの地域では現在、8月13日から16日にお盆を行いますが、
もともとは旧暦の7月15日を基準にしていました。
東京などでは7月に行う地域もありますが、これは昔の習慣に基づくものです。
お盆の期間とその重要な日々
お盆はいくつかの重要な日に分けられています。
7月13日または8月13日は「盆の入り」と呼ばれ、お盆の期間が始まります。
7月16日または8月16日は「盆明け」であり、送り盆として知られています。
中日、つまり7月14日から15日や8月14日から15日には、
通常、供養や法要が行われることが多いです。
お盆の起源
お盆の起源には二つの説があります。
一つ目はインド発祥説です。
古代インドで釈迦が教えを説いた時代に、
毎年7月15日に先祖の霊を祀る「ウランバナ」という行事が行われていました。
これが中国を経由して日本に伝わり、「盂蘭盆会」として知られるようになりました。
この行事には、釈迦の弟子である目連尊者が自身の母親を餓鬼道から救う話が含まれています。
二つ目の説は、日本で発祥したとするものです。
日本では古来から霊を祀る風習があり、その一環としてお盆が行われてきました。
夏の期間に先祖の霊を迎えるために「ボニ」と呼ばれる容器を使用し、
これが言葉の転訛を経て「お盆」と呼ばれるようになりました。
迎え火と送り火について
お盆の最初の日には迎え火を行い、これによって故人や祖霊が迷わず家まで来ることができるようにします。
送り火はお盆の最終日に行われ、故人がこの世を後にしてあの世へと戻る道中を照らすために行います。
一部の地域では送り火として灯籠流しも行われます。
新盆・初盆について
新盆、または初盆とは、故人が亡くなってから最初のお盆を迎えることを言います。
これは通常、亡くなってから四十九日を経過した後のお盆に該当します。
もしお盆に四十九日が重なる場合は、翌年のお盆で新盆(初盆)を迎えます。
新盆の際には、一般的にはお坊さんを家に招いて、法要を執り行うことが多いです。
新盆では、故人の親族だけでなく、友人やかつての知人も招かれることがあります。
法要後は、精進料理で参列者をもてなし、この時お坊さんも同席することがあります。
このため、新盆には丁寧な供養とともに正装をするのが普通です。
お坊さんを呼ぶ場合は、お盆期間中は非常に忙しくなるため、早めに連絡を取り予約を入れることが重要です。
盆棚について
盆棚、または精霊棚として知られるこの場所には、仏具やお供え物を置きます。
お盆には先祖が一時的にこの世に戻るため、家に適切な場所を設けることが大切です。
この場所の準備がなければ、霊たちが戻る場所がなくなってしまいます。
盆棚やお仏壇は、仏教のさまざまな宗派で見られる習慣ですが、地域や寺院によって異なることがあります。
盆棚に準備するものには、それぞれ意味が込められています。
たとえば、マコモと呼ばれるイネ科の植物は、昔、釈迦が病人を治療するために使用した寝床に
使われたことから、盆棚に敷かれるようになりました。
また、ほおずきはその形が盆提灯に似ており、故人や祖霊に場所を示す目印として供えられます。
水の実は、蓮の葉の上に茄子やきゅうりを乗せ、洗ったお米を盛り付けたもので、
すべてのご先祖様に食べ物が行き渡るような意味が込められています。
これらの供え物は、釈迦が施餓鬼を行ったことに由来し、飢えた先祖への供養として行われます。
盆棚には、必ずしも特定の形式に従う必要はなく、祖霊を供養する気持ちがあれば、
座卓やテーブルを使用することも可能です。
新盆の際は白提灯を、翌年からは色とりどりの提灯を用います。
また、お供え物には精霊馬を含め、
「五供」と呼ばれる5つの要素―お香、お花、明かり(灯燭)、水、食べ物―が必要です。
これらは先祖の霊をもてなすための要素とされています。
五供(ごく)と呼ばれるお供えの基本
精霊馬について お盆の期間中には、精霊馬として知られるきゅうりやナスを馬や牛に見立てた飾りが一般的です。
これらは、つまようじや割り箸で脚を作り、盆棚に飾ります。
きゅうりは速く走る馬を象徴し、先祖が早く帰ってくることを願う象徴です。
一方で、ナスは歩みが遅い牛を表し、ゆっくりとあの世に戻り、
多くのお供え物を運べるようにという願いが込められています。
これらは夏に旬を迎える野菜であるため、この時期に用いられるのです。
お墓参りのタイミングについて
通常、お墓参りはお盆の初日に行われることが多いですが、実際には人それぞれ異なります。
一部では、お盆の入りである13日に迎え火をしてから、14日や15日にお墓参りを行い、
16日に送り火をするという流れがあります。
これにより、合計で3回お墓を訪れることになります。
個人的には、ご先祖を迎える前にお墓の周囲をきちんと掃除することが望ましいと思います。
墓石の意味について
お盆の期間中、お墓参りが行われるのは、祖霊が自宅に滞在しているとされるためです。
お墓は本来、先祖を祀る場ではなく、本尊を拝むための場所とされています。
故人は普段この世には戻ってこないため、本尊を拝んで故人の供養を行うことが一般的です。
したがって、お墓は霊界とこの世の接点とされ、いつ参拝しても意味があるとされています。
迎え火について
迎え火は、できるだけ日が暮れる前に行うのが好ましいです。
これにより、故人の霊が寂しくなることなく、家庭に戻ることができます。
夜遅くになると、故人が家族に迎えられなかったと感じ、寂しい思いをする霊も出てくるかもしれません。
ただし、中日にお墓参りをする場合、成仏していない霊がついてくる可能性があるため、
自宅に帰った際は塩をまくことが一つの対策です。
お盆のお墓参りに用いる花について
お盆のお墓参りで用いる花は、故人が生前好んでいた花でも問題ありませんが、
新盆の際には遺族の感情を考慮して、故人が特に好んだ花を避けるべきです。
これは新盆で故人の死を悼む際に、その花が遺族にとって悲しみを再び呼び起こす可能性があるためです。