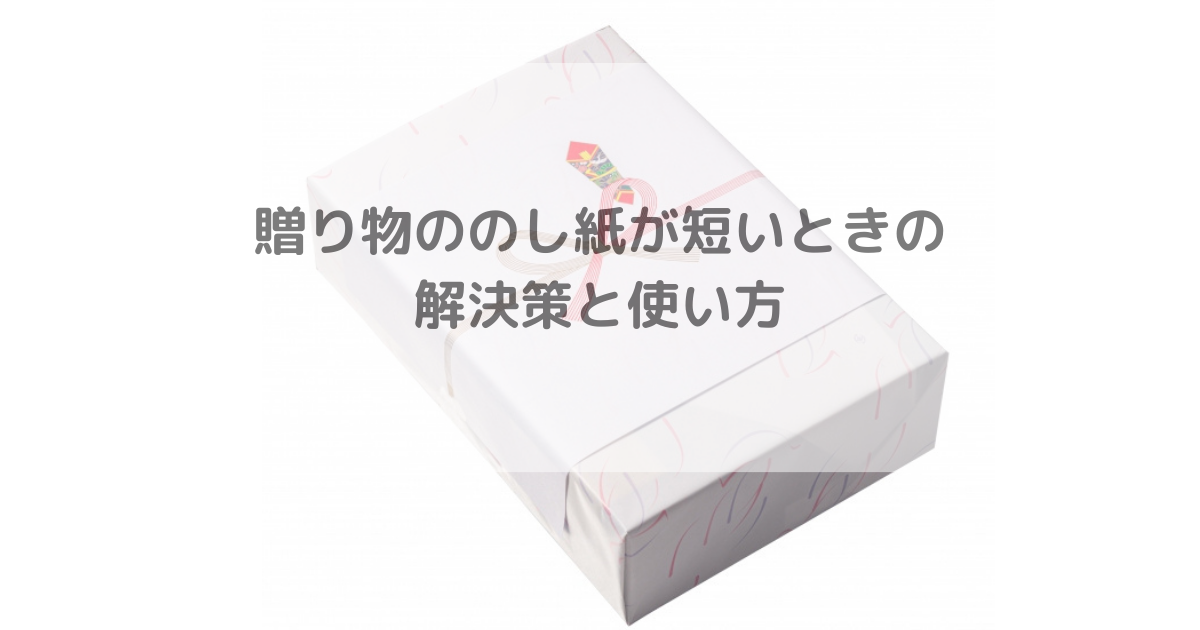贈り物に欠かせないのし紙ですが、時には用意したのし紙が贈る品の大きさに対して短すぎる場合があります。
このような状況は意外と多く、市販ののし紙はサイズが限定されているため、
特に大きな贈り物を包む際に困ることがあります。
最も一般的で手に入りやすいのはB4サイズです。
この記事では、のし紙の長さが不足した場合の対応策と、適切なのしの使い方をご紹介します。
大切な人へのプレゼントがより喜ばれるように、この情報をお役立てください。
対処法としては、以下の3つが考えられます。
- 必要に応じて大きなサイズののし紙を用意し、カットして使用する
- 置きのしを選択する
- 短冊のしを利用する
それぞれの方法について、実用的なアプローチを詳しく解説します。
のし紙の適切な使い方
のし紙は、水引が贈り物の中央に来るように箱に貼り付けます。
縦は箱の端が少し見える程度、横は箱を一周して裏でつながるようにします。
箱の裏でのし紙が重なる際は特に注意が必要です。
祝い事の場合は右側を上にし、弔事では左側を上にするのが通例です。
のし紙が短くて両端が届かない場合は、可能な限り回して貼ります。
もし横幅が足りなければ、左右が見えてしまい見栄えが悪くなるので、対処が必要です。
対処法としては、適切なサイズののし紙を選び、必要に応じて上下を切り揃えて使用することがあります。
利用可能なのし紙のサイズは多岐にわたり、例えばA5から大反物判までのサイズがあります。
切る際は水引と平行になるように注意し、視覚的なバランスを崩さないようにすることが重要です。
置きのしを活用する
置きのしは、和紙に水引を結んで作られたもので、これをプレゼントの中心部に設置します。
特に結納品や結納返しに用いられることが多く、大きなプレゼントにも適しています。
短冊のしを選ぶ
短冊のしを使用すると、プレゼントの横幅に関係なく適用できます。
特にのし紙が短い場合に便利で、略式ですが一般的な贈り物に使用しても問題ありません。
短冊のしは通常、プレゼントの右上に配置し、美しく見えるように注意して貼り付けます。
使用する際は、両面テープを利用すると簡単に固定できますが、
のりで貼る場合は紙が伸びるのを防ぐため注意が必要です。
弔事の場合は左上に配置するのが一般的ですが、地域によっては右上に貼る場合もあります。
北海道では、慶弔に関わらず中央右側に配置する習慣があります。
のしに関するその他の注意点
のし紙はただの装飾ではなく、その起源や使用する際のエチケットが重要です。
のしとは本来、「のしあわび」が由来で、長い歴史を持ち、神事などで用いられてきました。
現代では、のし紙を使う場合、内のしと外のしの二種類の方法があり、
その選択は贈る相手や状況によって異なります。
また、のし紙は見た目だけでなく、贈り主と贈り物の内容が一目で理解できるようにするための
重要な役割を果たします。
のし紙の種類と色、それぞれの使い方
のし紙には色と形状の違いにより、
紅白蝶結び、紅白結び切り、黒白結び切り、黄白結び切りの四つの主要なタイプが存在します。
これらは以下の用途に応じて使い分けられます。
紅白蝶結び
このタイプは、紅白の水引が蝶のように結ばれており、再結びが可能なため、
繰り返しの祝事に適しています。
一般的には祝事全般、出産祝い、お中元、お歳暮などに使用されます。
紅白結び切り
紅白の水引を固く結び、容易に解けない形式です。
結婚祝いや退院祝いなど、一度限りの重要な節目で用いられることが多いです。
黒白結び切り
黒と白の水引で堅く結ばれたもので、のし紙を使用せず、主に葬儀や法事での供え物に使われます。
黄白結び切り
黄色と白の水引が堅結びで、お供え物や法事の際に使用されます。
特にお盆や法要に適しています。
地域による風習の違いに注意が必要で、一般的には黒白の水引が葬儀で使われますが、
地域によっては黄白の水引の使用時期が異なるため、慣例を確認することが推奨されます。
水引の本数
水引の本数には、3本、5本、7本、10本などがありますが、一般的には5本が基本とされています。
この5本は中国古代の「五行説」に基づくもので、
自然や人間の万物が五つの元素で構成されているという考えから来ています。
また、奇数が好まれるのは、「割り切れない数であること」や中国の陰陽の考えが背景にあります。
10本の水引は5本を二倍にしたもので、より豪華な装飾を意味します。
のし紙の表書きと名入れ
表書きは、のし紙の上部に記されるもので、贈り物の目的を示します。
一般的な祝いごとである入学、成人式、出産では「御祝」や
具体的なイベント名(「御入学祝」「祝成人」など)を記載します。
これらの祝い事は繰り返しが可能なため、紅白蝶結びの水引を使用します。
お返しには「内祝」「粗品」と記すことが一般的で、
出産のお返しの場合、赤ちゃんの名前を入れることがあります。
結婚祝いには「御結婚御祝」「寿」を記載し、結婚が一度きりのイベントであるため、
紅白結び切りの水引を用います。
長寿祝いでは「福寿」「祝還暦」などを使用し、紅白蝶結びの水引を使います。
快気祝いでは、「祝 御退院」などと記し、繰り返し望まれないため紅白結び切りの水引が適しています。
年始には「御年賀」、お中元やお歳暮、暑中見舞い、寒中見舞いにはそれぞれ
「御中元」「御歳暮」「暑中御見舞」「寒中御見舞」と書きます。
神事では、「奉納」や「奉献」と記し、最初の米を供える際は「御初穂料」を記載します。
仏教の場合は宗派によって「御霊前」や「御仏前」が使われ、
キリスト教では「お花料」や「御花料」を使用します。
名入れは、水引の下に贈り主の名前を記す部分で、
職場で複数名で贈る場合は年齢や職位が高い順に、夫婦での贈り物は男性名を右に記します。
出産祝いのお返しでは、赤ちゃんの名前のみを記入し、ふりがなも添えると親切です。
まとめ
のし紙が短い場合の解決策
- 大きめののし紙を適切なサイズにカットして使用する。
- 置きのしを選択して、贈り物に直接配置する。
- 短冊のしを利用し、サイズの制限なく贈り物に適用する。
のし紙は多様な形式が存在し、それに応じた表書きもさまざまです。
のし紙の長さに困ったときは、これら三つの方法で対応可能です。
適切なのし紙とマナーを理解することで、贈り物をさらに特別なものにし、
受け取る方に喜んでもらいましょう。